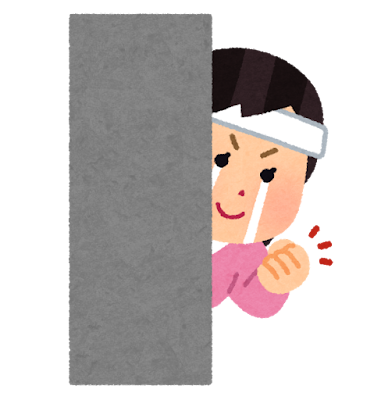こんにちは。畑です。
前回のブログで2024年の税理士試験の勉強方法について書くとお伝えしてから、1年の期間が空いてしまいました…💦
1年後の現在はというと、2025年の試験が終わり結果を待っている状況です。
ブログの更新を再開し、2024年の試験結果と2024年・2025年の勉強方法、そして2025年の試験結果まで書き切りたいと思います!
2024年試験直前の状況
前回のブログでお伝えしていたように、2024年は財務諸表論と消費税法の2科目を受験しました。どちらも1回目の受験です。直前期の6月に受けたTACの模試の結果は、公開できないくらい散々な結果でした。(前回のブログでしっかり公開しているので気になる方はご覧ください。笑)http://【税理士受験記】20代女性税理士を目指して⑦
散々な模試から約2か月間でどれくらい成長できたでしょうか。結果は、何とか本試験で戦える!と思えるレベルにはもっていけました。仕事をしながら2か月間でここまで仕上げることは難しかったと思いますが、試験勉強に専念させていただいていたので急成長できましたし、急成長しないわけにはいかなかったです(^^)

先生のスピード感に負けないように必死でした💦
本試験直前の仕上がり具合についてはもうあまり覚えていないのですが、財務諸表論の理論に関しては、理論の重要箇所がまとまっている”ポイントチェック”をひたすら暗記。一言一句というほどは暗記できていなかったです。計算は、総合問題を解きまくって平均で40/50点を取れるくらいで、基本的に時間は足りているが、5問中1問くらい解き切るには時間が少し足りないという感じだったと思います。
消費税法については、理論はTACの”理論マスター”のAランクBランクの理論は暗記、Cランクは内容を理解しているくらいだったと思います。加えて、2024年の税理士試験がインボイス元年だったので、インボイス関連の知識を国税庁HPから集めて、徹底的に詰め込みました。インボイスに関する通達やQ&Aがまとまっているページがあったので、すべて目を通しました。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
理論が不安だったこともあり、計算についてはほとんど記憶に残っていないです…。試験時間2時間の内、理論50分・計算70分で解くようにしていましたが、70分で解き切れることは試験直前でもほとんどなかったと思います。
試験当日!
受験地は一番近い石川県で、会場は金沢市にある地場産業振興センターです。午後からの受験なので試験当日に自宅から会場に向かっても間に合うのですが、去年に引き続き山本先生が受験時に宿泊して合格したという縁起の良いお宿に前泊させていただきました。お宿も受験会場も去年と同じだったので、スムーズに会場入りでき一安心でした。会場についてからは、YouTubeで脳を活性化させる音楽を聴きながら、おにぎりとブドウ糖ゼリーを摂取して脳のコンディションを整えました。計算のミスノートを確認し、ポイントチェックに目を通していざ財務諸表論の試験に臨みました。

2023年、2024年、そして2025年も試験当日の朝に食べました。
勝負飯!
試験の出来はというと、理論は第2問の記述が全く分からず白紙の部分もありました。計算は全く時間が足りず、3割ほど埋められていなかった気がします。残り時間が少なくなったときに未回答の箇所を解き進めるか、回答した箇所の見直しをするかで一瞬判断を迷った場面がありました。本試験では思うように解き進められていなかったので、見直すより解き進めたいと思ったのですが、他の人が取れている箇所を確実に得点することの大切さをTACの講義で学んでいたので、見直しに切り替えました。終了1分前くらいに間違いに気づき、最後の最後で修正できたので、終了直後は助かった…という気分でした。勉強期間中の答練では見直しよりも解き進める方を優先してしまいがちで点数をとれるところを凡ミスで落とすという事がちょこちょこあったので、同じ失敗を本試験でしなくて良かったです。見直さないといけないと思いながらもついつい解いてしませんか…?
理論も計算も手ごたえがなく答案回収の時間は絶望していましたが、回収時に目に入った周りの受験生の答案もあまり埋められていないようでほっとしたのを覚えています。おかげで絶望を引きずらずに次の消費税法に望めました。
消費税法については、初税法ということで財表よりも気合が入っていました。勉強時間も財表の倍くらいはあったんじゃないかなと思います。インボイス導入後初めての試験なので、インボイスがどのような形で出題されるのかドキドキしていました。財表の試験が終わって気が緩んだり集中できなくなったりするかとも思ったのですが、自然とすぐに次の消費税法に気持ちが向かっていました。2個目のブドウ糖ゼリーを食べながら、最後の見直しを行いました。最後はやっぱりインボイスを中心に見直して試験に臨みました。
最後の見直しが功を奏したのか、理論はよく書けたと思います。媒介者特例以外は、不足部分はありながらも結論を合わせられた自信はありました。媒介者特例も、目を通したことはあったのでなんとなくで書きました。正直、理論問題にざっくり目を通したときに、べた書きが少なくて助かった…と思っていました。事例問題の方が好きでした。理論→計算の順で解き進めたのですが、予定通り理論を50分で解いて計算に進みました。計算は2問あって、2問とも2割特例の適用有無を問われる問題で、納税義務は出題がありませんでした。計算問題をある程度解き終わった時に、20分くらい時間が残っていました。頭の中が「???」でした。見直して2割特例の適用があっても有利判定のために原則の計算も必要だ!となり、慌てて仕入税額控除の振り分けをしました。試験終了直後は理論の手応えがあったものの、みんな書けているんじゃないかと思いましたし、計算はこれまでの答練にはない形の問題だったので、手応えも何もありませんでした。合格への不安や後悔などはなく、少しの達成感ととにかくふわふわした感覚でした。
次回に続く
ウィズ総合事務所では、現役スタッフによる資格取得に向けた受験記をブログで発信しています。簿記や税理士試験の勉強中の方や、これから目指す方はほかのスタッフの記事もぜひご覧ください。>>スタッフブログを見る